
自宅でできる高次脳機能障害のリハビリ
高次機能とは、大脳で営まれる様々な機能のことで、知覚、認知、記憶、注意、判断、情動、言語、行為などが高次脳機能に含まれます。日常生活や社会活動で必要なスキルや能力に直結しています。高次脳機能が損傷すると無意識でできていたことができなくなる場合もあります。

高次機能とは、大脳で営まれる様々な機能のことで、知覚、認知、記憶、注意、判断、情動、言語、行為などが高次脳機能に含まれます。日常生活や社会活動で必要なスキルや能力に直結しています。高次脳機能が損傷すると無意識でできていたことができなくなる場合もあります。
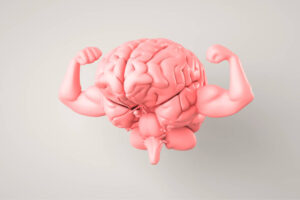
脳梗塞に起因する感覚障害は、適切なリハビリを通じて回復の道を歩むことが可能です。運動障害と併発して感覚障害が発生している場合には、通常は両方を対象としたリハビリが実施されます。リハビリの効果は、年齢や障害の重度によって変動しますが、早い段階からのリハビリの介入での改善が期待されます。

回復期リハビリテーションでは、患者様の回復能力が高まるため、集中的なリハビリテーションが特に有効とされています。そのため、この時期に特化した専門医療機関も国内各地に設けられています。そして、患者様が朝から夜まで過ごす入院生活全体を一つの大きなリハビリとして捉えます。

頸髄には四肢の運動や感覚を伝達する神経が走行しているため、頸髄損傷によって四肢麻痺などが生じ、日常生活に大きな支障を与えます。また、心臓の動きをコントロールする神経や呼吸能力を司る神経にも影響を及ぼすため、最悪の場合血圧低下や呼吸停止などに陥ります。

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血からなる脳卒中は、日本全国で110万人をこえる患者様がいて、年間10万人以上が命を落とす疾患です。急性期治療の進歩により救命率は格段に向上し、後遺症に対する治療が課題となっています。再生医療が持つ、新たな治療としての可能性に注目が集まっています。

脳梗塞とは、脳の血管が詰まり、脳に障害が起こる病気です。脳梗塞で生じた障害を治療・回復させるためにはリハビリは欠かせません。この記事では、脳梗塞の基本的な知識とともに脳梗塞に対して行うリハビリ内容や期間、再生医療とリハビリの関係性について解説します。

脊髄損傷は主に交通外傷や転落によって脊髄を損傷してしまうことです。脊髄には様々な神経が走行しており、損傷によって多くの機能に障害が起こる可能性があります。麻痺やしびれの他に嚥下機能が障害になることもあり、食事摂取困難や誤嚥性肺炎のリスクを高めてしまう可能性もあります。

脳卒中や交通事故などの後遺症で知られる高次脳機能障害には様々な症状があります。高次脳機能障害は日常生活だけでなく仕事にも大きく影響しますが、麻痺のように外からはっきりとは見えにくいため、周囲の配慮も必要です。この記事では高次脳機能障害の中でも注意障害と遂行機能障害について解説します。

ラクナ梗塞は脳の深部にある細い血管(穿通枝)が閉塞することで起きる脳梗塞です。動脈硬化が主な原因です。体の片側の運動麻痺や感覚障害が起きることがあり、後遺症として残る可能性があります。生活習慣の改善と急性期治療、再発の予防が重要であり、再生医療の可能性にも注目が集まっています。
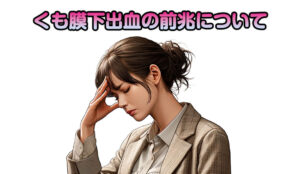
くも膜下出血とは脳の血管が風船状に変化して膨らみ、脆くなった部分が急に破裂して生じる病気です。これまでくも膜下出血はなんの前兆もなく急に発症すると考えられてきましたが、最近の調査・研究の結果、前兆とも言える特徴的な症状を認めることがわかってきました。