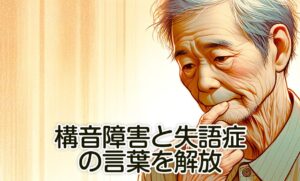
最新治療技術で構音障害と失語症の言葉を解放する
脳血管障害などで構音障害・失語症などが出現すると、会話の表出や理解に支障が出るため、うまくコミュニケーションを取れなくなってしまいます。
それに対し、これまで言語療法が行われてきましたが、最近では医療の発達とともに新たな治療法も評価されています。
そこでこの記事では、構音障害と失語症のための最新治療技術について紹介します。
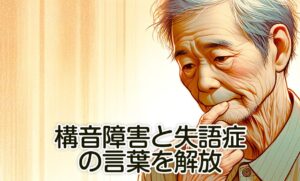
脳血管障害などで構音障害・失語症などが出現すると、会話の表出や理解に支障が出るため、うまくコミュニケーションを取れなくなってしまいます。
それに対し、これまで言語療法が行われてきましたが、最近では医療の発達とともに新たな治療法も評価されています。
そこでこの記事では、構音障害と失語症のための最新治療技術について紹介します。

脊柱管狭窄症とは脊柱管が狭窄して、内部を走行する脊髄や周囲の神経が圧迫されることでさまざまな症状をきたす病気です。
主に頸椎や腰椎で生じやすく、進行すれば手術が必要となることもあるため、早期に適切な診断・治療を受けることが大切です。
この記事では、脊柱管狭窄症の定義や原因、診断方法などについて紹介します。

脳出血後には、なるべく早めにリハビリを開始することが大切です。脳出血発症数ヶ月後には、回復期のリハビリをすることが必要となります。この記事では、脳出血後の回復期にやっておくべきことについて、リハビリや復職、運転再開など社会復帰のためのポイントも解説していきます。

脳梗塞とは、高血圧や糖尿病、脂質異常症などのために動脈硬化が進み、脳の血管が詰まってしまうことで起こる脳の病気です。脳梗塞の予防や対策のためには、健康的な生活習慣が鍵となります。今回の記事では、脳梗塞を予防するためにはどのような生活習慣を送れば良いのか、実際に食生活や運動習慣の例をあげて解説していきます。

脳梗塞発症後、急性期治療を経て病状が安定した後は自宅生活や社会復帰を目的とした慢性期治療に移行します。
慢性期は後遺症と向き合う期間であり、しっかりとリハビリを行うことが重要です。
また、脳梗塞の再発予防に努める期間でもあります。
この記事では、脳梗塞の慢性期にやっておきたいことについて詳しく解説します。

脳出血は緊急性が高く、治療前や急性期には素早い対応が求められます。回復期や慢性期には再発予防に加え、生活の支援が重要になります。病気の段階により求められる対応や観察項目が異なるため、正しい知識を持って看護にあたる必要があります。後遺症対策のため再生医療の効果に期待が高まっています。
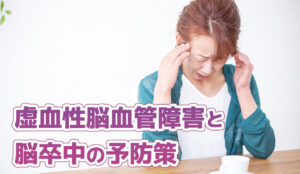
脳卒中はくも膜下出血や脳出血・脳梗塞の総称であり、脳細胞の血流が低下することで麻痺やしびれなど、日常生活に大きな支障をきたす後遺症の原因となります。そのため、食事や運動などの生活習慣を整え、未然に発症を予防することが重要です。この記事では、虚血性脳血管障害と脳卒中の予防策について解説します。

言葉をうまく発せられない場合、構音障害もしくは 失語症 の可能性があります。構音障害は、声を出すための喉の筋肉などの器官がうまく働かない場合に起こり、失語症は大脳の中で言語をつかさどる言語中枢といった部分が障害された場合に起こります。今回の記事では、この構音障害と失語症について、違いについても触れつつ解説していきます。

痙縮(けいしゅく)とは、筋肉が過度に緊張し、手足の動きが制限される、または意図しない動きが起こる状態を指します。脳卒中の後遺症には、よく見られる症状の一つです。例えば、手の指が常に握られた状態で開きづらくなったり、肘が自然に曲がったり、足の先端が足の裏側に向かって曲がるなどの動きが現れます。

急性期リハビリテーションとは、骨折や病気なども含め発生した直後、またはその治療と同時に実施されるリハビリのことを言います。通常、このリハビリテーションフェーズは発症後数日から約1ヶ月の間に展開されることが多いです。近年では早期から開始することが推奨されています。